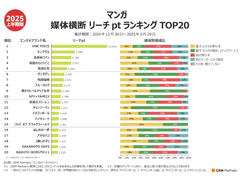日米のアニメーション製作が抱える課題とデジタル・ファーストの可能性:ANIAFF連携プログラム「WIA代表マーガレット・M・ディーン×東映アニメーションプロデューサー関弘美対談」
公開日: 2026/01/20
あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバル(ANIAFF)にて12月14日、連携プログラム「Women in Animation(WIA)代表 マーガレット・M・ディーン×東映アニメーションプロデューサー関弘美対談」が開催されました。Skybound Entertainmentのスタジオ責任者としてアニメ『インビンシブル 〜無敵のヒーロー〜』などをはじめとするオリジナル作品制作を統括するディーン氏と、『おジャ魔女どれみ』や『デジモンアドベンチャー』を手掛けた日本アニメ業界における女性プロデューサーのパイオニアである関弘美氏。日米を代表する二人のプロデューサーが、資金調達からスタッフ確保、市場の変化まで、日米の状況を比較しつつ、アニメーション製作の現在について深く語り合いました。
※本記事で触れられている内容は2025年12月時点の情報です。
 左から
マーガレット・M・ディーン氏、関弘美氏
左から
マーガレット・M・ディーン氏、関弘美氏
- 日米プロデューサーの原点にみる文化的差異:「ファイナンス主導」と「作り手主導」
- 企画成立に必要なスキル:「カバレッジ」「ピッチング」
- 人手不足の日本、仕事不足のアメリカ
- 子ども向け市場における「デジタル・ファースト」の可能性
日米プロデューサーの原点にみる文化的差異:「ファイナンス主導」と「作り手主導」
マーガレット・M・ディーン氏と関弘美氏がプロデューサーの道を歩み始めた動機には、文化的な差異が見て取れました。関氏は、学生時代に実写の子ども番組のシナリオを書いた際、演出内容が自身の望む形にならなかった経験がありました。その際、「シナリオを書くだけではなく、演出もちゃんと学ばないと、自分が望むような作品はできない」と決意し、演出や全体を掌握するプロデューサーの道しかないと考え、東映アニメーションの門を叩いたといいます。
一方、ディーン氏は、自身が実験映画やビデオ作品を作る中で、「自分がやりたい活動のすべてを、自分一人でお金を払って賄うことはできない」と痛感したことが契機となりました。彼女は当時、「プロデューサーこそが、映画を作るための資金を集めてくる人なんだ」と考え、作品をコントロールするためにカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)でプロデューシングを学んだことを明かしました。
この“資金”に対する意識の差は、日米の業界構造の違いを反映しています。ディーン氏は、「アメリカで生活し、働くうえでは、資金調達があらゆることの根底にある」と述べ、自身の労働者階級出身という背景もあり、資金へのアクセスがクリエイティブな選択を左右する現実を強調しました。
対して関氏は、日本のプロデューサーは「まず作ることを考える」傾向が強く、自身も若い頃はどのクリエイターと作るかを優先していたと語ります。関氏が資金調達の重要性を強く意識したのは30代半ばになってからであり、日本では中間管理職以上になるとお金のことを考え始めることが多いとの経験を共有。また、「自分の所属している会社からお金を出してもらう」ことが重要だと訴え、その利点を「組織やスタッフが(製作を)バックアップしようという気持ちになる」と説きました。
企画成立に必要なスキル:「カバレッジ」「ピッチング」
 マーガレット・M・ディーン氏
マーガレット・M・ディーン氏
対談では、企画を成立させるための具体的な技術についても議論が及びました。 ディーン氏がハリウッドで企画開発に携わる人の最初の一歩として挙げたのが、「カバレッジ」を書く能力です。これは脚本や資料を読み解き、あらすじや要約、プロジェクトの価値を短時間で提示する文学的素養を指します。同氏は、ハリウッドではストーリーが製作の核であり、「カバレッジを書くスキルは、資金を調達したり、プロジェクトをスタジオや配信プラットフォームに売り込むために不可欠である」と述べました。
関氏もこの手法の重要性に同意しています。関氏は、アメリカでカバレッジを学んだ大学の先生に教えを乞い、その後独学で学んだことを明かし、「出資側と同じ言葉で企画書を書くことは、説得力を獲得するために非常に有効だった」と振り返りました。
そのほか、プロデューサーや企画開発担当者が持つスキルとして紹介されたのが「ピッチング」と「エレベーター・ピッチ」です。ディーン氏は、相手の頭の中で映画を体験させるように語るピッチングを「一つのアート」と呼び、プレゼン資料である「ピッチ・バイブル」は、多忙な相手を数分で説得するために「極めて簡潔で、要点が的確にまとまっている必要がある」と強調しました。特に「エレベーター・ピッチ」は、エレベーターに乗り合わせた1〜2分の間にプロジェクトの魅力を伝える手法であり、あらゆる売り込みの必須条件であると語りました。
これに対し関氏は、若手時代に先輩プロデューサーのために大量の企画書を書いた経験に触れ、「本命の企画を良く見せるために、あえて80点くらいの企画書を何本か書くスキル」を磨くことを通じて、様々なことを学んだエピソードを明かしました。ディーン氏はこの戦略を「非常に賢明なやり方」と評しました。
人手不足の日本、仕事不足のアメリカ
現在のアニメ制作現場において、日米は真逆の課題に直面していることが浮き彫りになりました。
関氏が指摘したのは、日本の深刻な「人材不足」です。企画が通り資金調達できても、作るスタッフがいないために着手できない状況が5〜6年続いているといいます。そして、「お金も企画もあるのに、作る人材がいなくて作り出すことができないことほど、プロデューサーを苛立たせる要因はない」と、現在の日本の窮状を訴えました。
一方で、ディーン氏が明かしたアメリカの現状は、日本とは対照的に「深刻な失業」です。配信プラットフォームが「キッズ向けコンテンツはビジネスとして成立しない」と判断し、制作本数を縮小。その結果、「正確な数字は分かりませんが、ロサンゼルスのアニメ従事者の50〜60%が失業しているという話も聞いています」と驚くべき数字を挙げました。
ディーン氏は、「日本はアーティストを必要としており、アメリカには仕事を必要としているアーティストがいる」という皮肉な状況を指摘し、このミスマッチを解消することが理想的な解決策であるとしつつも、円安や複雑な課題が実現を阻んでいる現状を関氏と共有しました。
子ども向け市場における「デジタル・ファースト」の可能性
 関弘美氏
関弘美氏
最後に、両氏はアニメーションの主要なターゲットであった子ども向け市場の変化について意見を交わしました。
関氏は、日本における少子化の進行により、未就学児童向けなどの番組制作が困難になっている現状を説明しました。日本のアニメが大人向けに偏るなか、関氏は「アジアやイスラム圏など、子どもの数が増えている地域に目を向けるべきだ」と述べ、他国の宗教や文化を学ぶ重要性を強調しました。
ディーン氏は、子ども向け作品が縮小されているなか、オリジナル・アイデアを売り込むことは非常に難しくなり、現在はゲームやコミックなどの「確立されたIP」に基づいたプロジェクトが優先されていることを訴えました。しかし、こうした閉塞感を打ち破る「デジタル・ファースト」の手法に希望があるとディーン氏は語ります。クラウドファンディングの「Kickstarter」などで資金を集めて短編を作り、YouTubeやSNSで先にファン層(オーディエンス)を構築してから、大手プラットフォームに交渉に行く手法です。ディーン氏は、「すでに数百万人の視聴者がいるという実績自体が、強力なピッチの材料になる」と、現代的な成功モデルを提示しました。 関氏もこれに強く同調し、「日本でもSNSでバズっているコンテンツは、企画を通すための強力なバックボーンになり得る」と述べ、オールドメディアと新しいメディアを融合させた発展の可能性に期待を寄せました。
今回の対談を通じて、日米のアニメーション業界は、手法や直面する課題(日本の人手不足とアメリカの失業)に違いはあれど、子ども向け作品市場の縮小といった共通の壁に突き当たっていることが明確になりました。しかし、両氏の議論は決して悲観的なものではありません。関氏が強調した「異なる文化圏への進出」と、ディーン氏が提示した「デジタル・ファーストによるオーディエンスの先行構築」は、これからのプロデューサーにとって不可欠な戦略となるでしょう。日米を代表する二人の知恵の共有は、グローバル化が進むアニメーションビジネスにおける、新たな可能性を照らし出しました。
取材・文 河西隆之
- 第1回:「アニメ」はなぜ世界で愛されるのか~「日本アニメとは何か? いま世界で何が起きているのか」(前編)
- 第2回:「アニメ」の発展が続く未来のために~「日本アニメとは何か? いま世界で何が起きているのか」(後編)
- 第3回:世界のファイナンスから学ぶコンテンツファンド再挑戦の成功要件:「コンテンツファンドは日本のアニメーションに多様性をもたらすか?」(前編)
- 第4回:製作委員会の限界を突破するキーワード「直接海外」「データによる客観性」:「コンテンツファンドは日本のアニメーションに多様性をもたらすか?」(後編)
- 第5回:日米のアニメーション製作が抱える課題とデジタル・ファーストの可能性:「WIA代表マーガレット・M・ディーン×東映アニメーションプロデューサー関弘美対談」
新着記事
-
2025年の動画配信(VOD)市場規模は推計6,740億円、3年ぶりの二桁成長率、2030年には8,953億円となる見込み
(2026/03/05) -
なぜ今、動画配信は「ライブ」へ向かうのか~ワーナーミュージック×U-NEXTが予測するOTTの未来
(2026/03/03) -
洋画・欧米ドラマからアニメへシフト、次の市場ブーストはスポーツに期待~定額制動画配信サービスの10年をデータで振り返る
(2026/02/26) -
『嵐』が初のTOP10入り、『リブート』『教場』の推しファン急増~2026年2月エンタメブランド調査結果
(2026/02/26) -
2025年の定額制動画配信市場規模は成長が再加速し6,000億円超え、Netflixがシェアをさらに伸ばし7年連続首位
(2026/02/25)
新着ランキング
-
音楽アーティスト リーチpt 週間TOP10【最新週】
(2026/03/05) -
マンガ リーチpt 週間TOP10【最新週】
(2026/03/05) -
映像 リーチpt 週間TOP10【最新週】
(2026/03/05) -
定額制動画配信サービス 週間リーチptランキングTOP20【最新週】
(2026/03/05) -
メディア横断リーチpt 急上昇TOP10【最新週】
(2026/03/05)
アクセスランキング
(過去30日間)
-
劇場公開映画 週末動員ランキングTOP10【最新週】
(2026/03/02) -
2024年の定額制動画配信市場は推計5,262億円、U-NEXTがシェア最大の伸び、6年連続首位のNetflixに迫る
(2025/02/25) -
2025年の定額制動画配信市場規模は成長が再加速し6,000億円超え、Netflixがシェアをさらに伸ばし7年連続首位
(2026/02/25) -
定額制動画配信サービス 週間リーチptランキングTOP20【最新週】
(2026/03/05) - ランキング ジャンル別一覧
-
競合ゲームファンからも支持される『Apex Legends』、人気PvPシューティングゲームの推しファン構成を分析
(2025/02/06) -
世界映画興行における日本モデル発信の重要性~シネアジア2025レポート
(2026/02/06) -
世界14カ国ゲームIP勢力図:圧倒的優位を誇る『マリオ』
(2026/02/13) -
2026冬アニメの盛り上がりを「推しファンデータ」で検証~『フリーレン』のけん引で過去最高クラスへ
(2026/02/20) -
世界で突出する日本映画・興行成功への注目~シネアジア2025レポート
(2026/01/30)